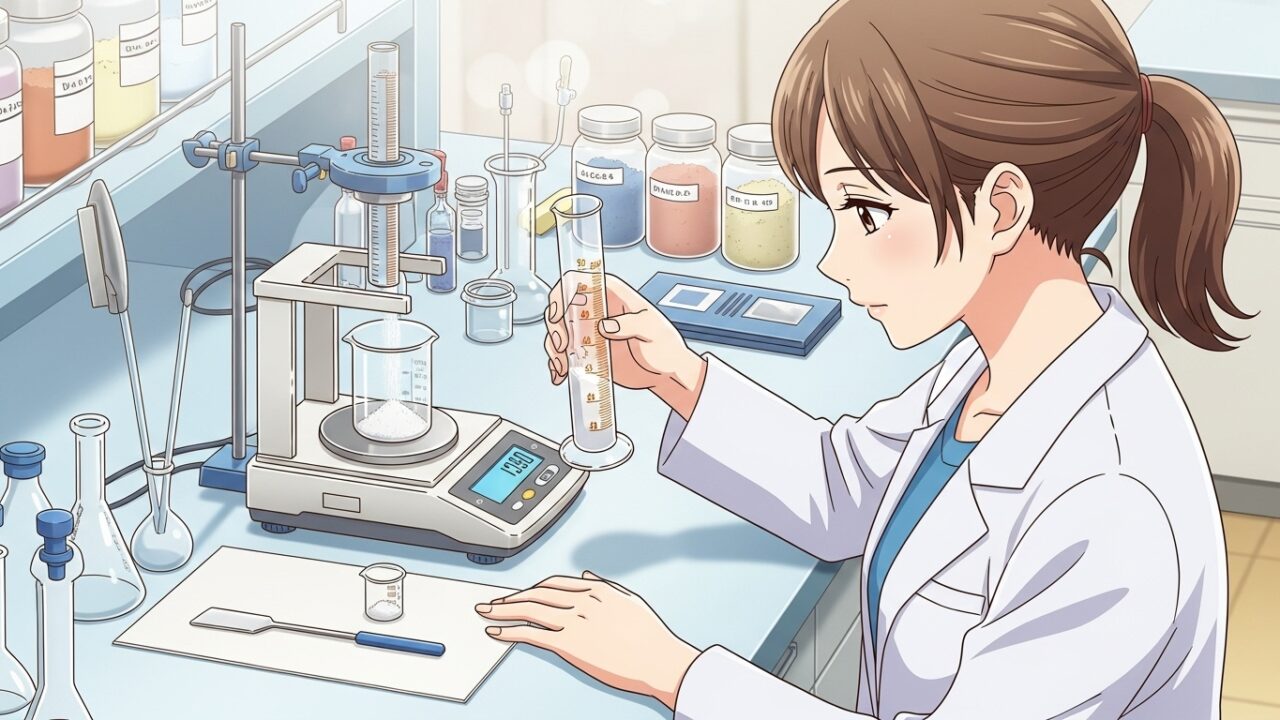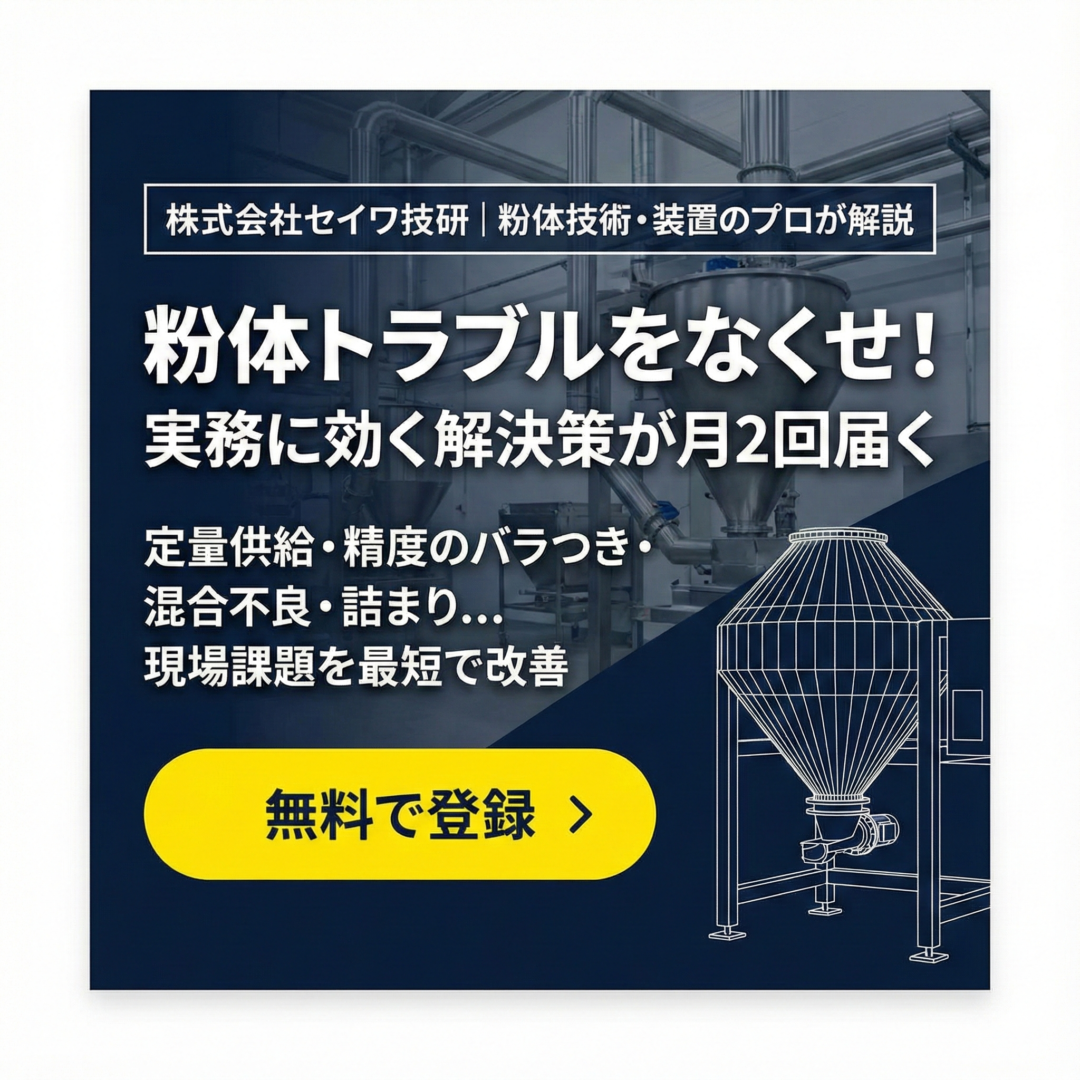1. 嵩比重とは?
「嵩比重(かさ比重)」とは、粉体を自然に容器へ充填したときの単位体積あたりの質量を指します。嵩密度、見掛け比重ともいわれますが、基本的には同様の意味と考えていただいて構いません。
たとえば同じ「1kg」の粉体でも、嵩比重が高い場合は小さな容器に収まり、嵩比重が低い場合は大きな容器が必要になります。
1-1. 真比重との違い
・真比重:粒子そのものの密度(空隙を含まない)
・嵩比重:粉体粒子がランダムに堆積したときの見かけの密度(空隙を含む)
粉体の挙動を考えるうえで、真比重と嵩比重を区別することは非常に重要です。
1-2. どんな業界で重要?
・食品業界:小麦粉、砂糖、調味料粉末などの定量処理に必須
・医薬業界:原薬や添加剤の定量処理に必須
・化学業界:ペレットや樹脂粉、顔料その他各種粉末の処理、輸送、計量設計
・金属・電池業界:粉末冶金や二次電池材料の供給安定化
2. 嵩比重の測定方法
嵩比重は、粉体の流動性や容器への充填状態によって変化します。代表的な測定方法を紹介します。
2-1. 簡易測定(じょうご落下法)
①粉体をじょうごから一定量落下させ、容器に自然充填させる
②容器に収まった粉体を擦り切り、内容物の質量のみを測定
③「質量 ÷ 体積」で嵩比重を算出
100cc容器に入った粉体の質量が64gだった場合、
64÷100=0.64
ということになります。
最も簡単で、研究所や現場でよく使われます。
当社が一般的に実施しているこの方法になります。

2-2. スコップ充填法
スコップで粉体をすくい取り、容器に落とし入れる方法。粒径が粗くても測定可能ですが、再現性はやや低めです。
2-3. JIS・ISO規格に基づく方法
JIS K 6721(プラスチック用粉体試験法)など、国際規格に準拠した測定方法があります。じょうごのサイズや落下高さを規定することで、より正確なデータが得られます。
2-4. タッピング法
粉体を容器に入れ、振動や打撃を加えて沈降させた後の密度を測定。
・嵩比重:自然充填状態(ふわっとした状態)
・タッピング:圧縮充填状態(できるだけ詰め込むようにトントンした状態)
→ 両者の差は「粉体の流動性や圧縮性」を示す指標になります。
3. 測定結果の活用例
嵩比重の測定は、粉体を扱う多くの工程に役立ちます。
3-1. 容器・包装設計
・嵩比重が低い粉体:大容量の袋やサイロが必要
・嵩比重が高い粉体:輸送効率はよいが、粉じん飛散等のリスクがある
3-2. 輸送・搬送機設計
スクリュー搬送、空気輸送の配管径やブロワ容量を決定する指標になる。
3-3. 粉体供給機の選定
・低嵩比重(かさ比重が小さい)粉体
→ 軽くて流れにくく、ホッパー内でブリッジが発生しやすい。
・高嵩比重(かさ比重が大きい)粉体
→ 流れやすいが、定量性が乱れやすく、供給量のバラつきが課題。
嵩比重は、供給の安定性を左右する「粉体性質」の目安を表す重要な数値といえます。
4. 嵩比重と粉体供給の課題
4-1. ブリッジ
低嵩比重の粉体は、ホッパー排出口に粉体が詰まりやすいため、流動性を確保する
ための補助装置が必要になります。
4-2. 定量供給の安定性
軽くふわふわの粉体はスクリューの回転に追従しにくく、供給量がバラつきやすい。
(回転数を上げても供給量が追従して増えない)
逆に高嵩比重粉体は過剰に流れてしまうことがあります。
(スクリューが停止した後も惰性で流れ落ちる)
4-3. 粉塵の飛散
非常に軽い粉体は供給中に舞いやすく、作業環境や歩留まりに影響します。
5. 当社の解決策:SMスクリューフィーダー
当社の SMスクリューフィーダー は、嵩比重が小さい粉体から大きい粉体まで、幅広い原料に対応できるよう設計されています。
・アジテータ付きホッパーでブリッジ対策
・スクリュー形状のカスタマイズで流動性に合わせた供給
・少量~大量まで安定した定量供給が可能
※実際の粉体を用いた「サンプルテスト(無料)」も実施可能です。
6. まとめ
・嵩比重は、粉体の見かけの密度を示す重要な指標
・測定方法は「じょうご落下法」「JIS規格法」「タッピング法」などがある
・測定結果は、容器設計・輸送効率・粉体供給機選定に活用できる
・嵩比重に応じた供給装置の選定が、安定した生産につながる