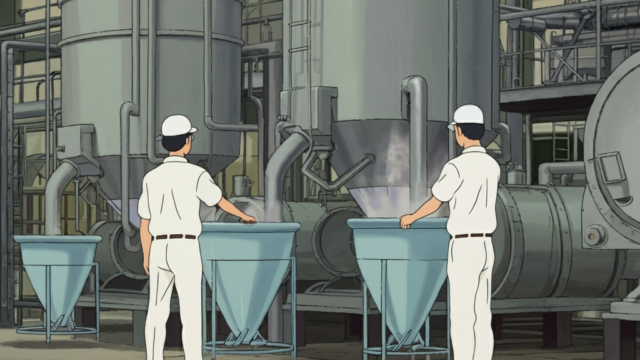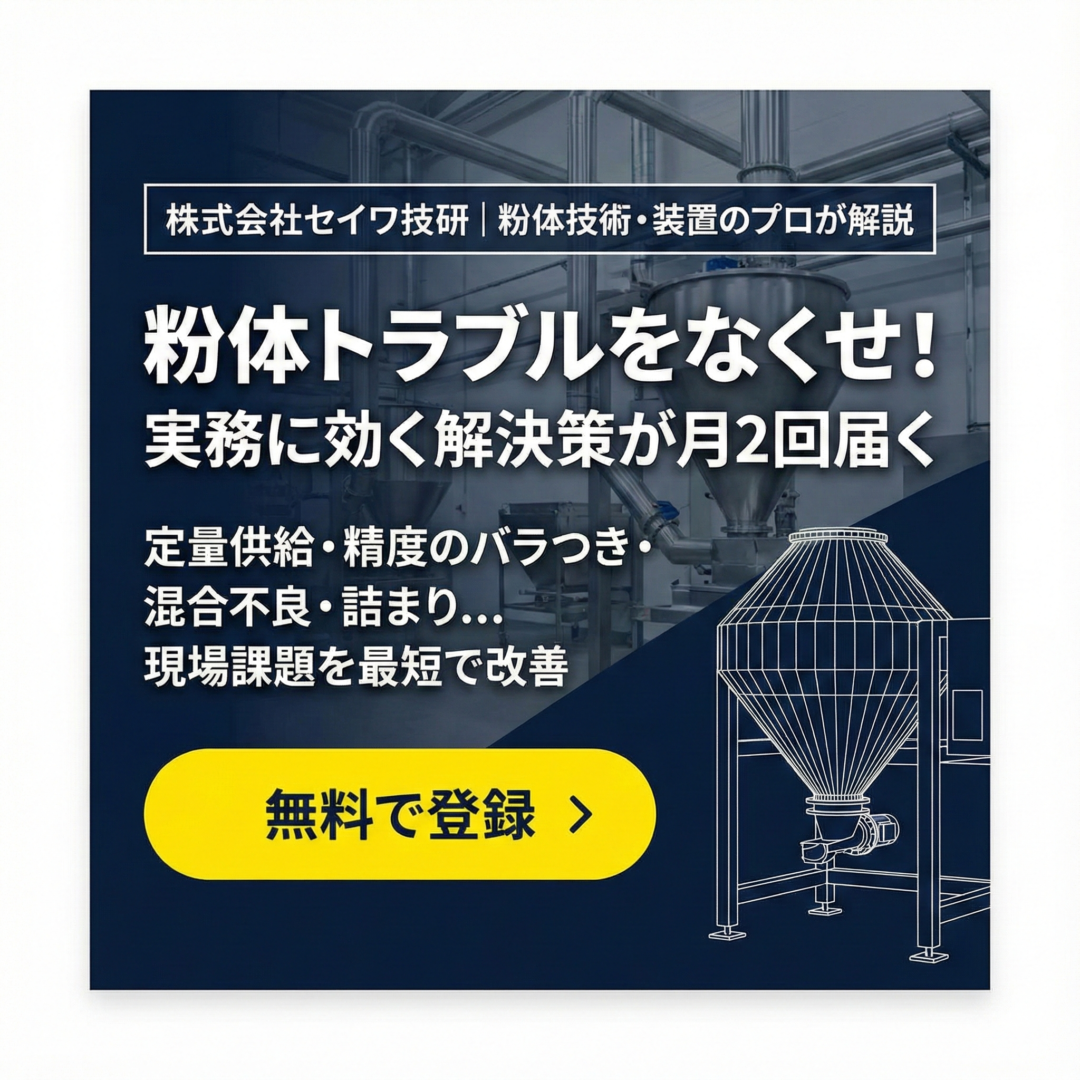混ざらない、分離する・・・粉体混合の永遠のテーマ
粉体を混ぜる作業はシンプルに見えて、実はとても奥が深い工程です。
同じ材料でも、「今日はうまく混ざったのに、別の日はムラが出た」「投入順を変えたら分離した」そのような経験はないでしょうか?
混合ムラの多くは、原料粉体の物性(粒度・比重・形状)に起因します。
この記事では、混合ムラの発生メカニズムと、その対策について解説します。
混合ムラとは? 均一混合と分離現象
混合ムラとは、異なる成分の粉が均一に分散していない状態を指します。
理想的な混合とは、どの部分を取っても同じ配合比で成分が含まれている状態です。
しかし実際には、混合中や排出時に比重の差による分離や、粒径の偏りが起きることで、
混合度が下がることがあります。
つまり混合ムラは、「混ざらない」だけでなく「混ざった後に再び分かれる」といった現象も含まれます。
混合ムラを引き起こす主な要因
1. 粒度差
粒径の大きい粉と細かい粉を混ぜると、細かい粉が空隙に入り込むため一見混ざったように見えます。
しかし、運転中の振動や落下で細かい粉が下に沈み、大粒が上に浮く「層分離」を起こしやすくなります。
特に、ふるい分けた後に粒度レンジが広い場合や、粗粉と微粉を同時に扱う場合に顕著に現れます。
2. 比重差
比重差が大きいと、混合中の運動で重い粉が沈降し、軽い粉が上に集まる現象が発生します。
この場合、どれだけ回転数を上げても完全には均一化しにくく、運転条件よりも混合方式や機構選定のほうが重要になります。
たとえば、自由落下や転動を利用するタイプ(V型、タンブラー型)は、比重差による分離が起きやすく、対してスクリューやリボンなど強制対流を起こすタイプは比較的ムラが少なくなります。
3. 粒子形状の差
球状・片状・繊維状など、形が大きく異なる原料同士を混ぜる場合もムラが出やすくなります。
片状や繊維状の粉体は絡みつきやすく、流動性が低下するため、撹拌による移動が不均一になります。
このようなケースでは、混合時間を延ばすよりも、撹拌羽根の形状や混合槽の傾斜角度を変えることで流動経路を見直すほうが効果的です。
混合ムラを防ぐための基本設計と運転の工夫
1. 原料投入順を工夫する
粒度や比重が大きく異なる場合は、軽い粉を先に入れて重い粉を上から加えることで沈降を抑えられます。
また、主原料に副原料を分散して投入するなど、順序を工夫するだけでも混合ムラが軽減します。
2. 混合時間・回転数の最適化
混合時間を長くすればよいというものではありません。
過混合になると、逆に分離や偏析が進む場合もあります。
テスト時に、時間経過ごとの「混合度(標準偏差など)」を測定し、最適条件を見極めることが重要です。
3. 混合槽内流動の“死角”をなくす
混合槽の形状や羽根の位置により、デッドゾーンが生まれると局所ムラが発生します。
混合機選定時には、混合槽内の粉体流動が全体に行き渡る構造かどうかを確認することがポイントです。
4. 混合直後の取り出し条件
せっかく均一に混ざっても、排出時に比重差で分離してしまうケースもあります。
このため、排出口の高さ・傾斜角・流速なども含めた取り出し設計も無視できません。
混合ムラ対策の実践例
たとえば、
・粒度差の大きい粉体 → 転動式より強制対流型へ変更
・比重差が大きい粉体 → 羽根角度を立てて上下対流を増加
・付着性のある粉体 → 内面バフ仕上げ+エアブロー補助
など、原料の特性に合わせた装置側の最適化が有効です。
また、実験スケールと量産スケールでは流動状態が変わるため、
スケールアップ時には混合時間をそのまま比例換算しないことも重要なポイントです。
まとめ ― 混合ムラは「原料物性×装置特性」の結果
混合ムラは単なる運転条件の問題ではなく、
粉体の粒度・比重・形状・表面性状など、物性要因と機械構造のバランスで決まります。
「なぜ混ざらないのか?」を正しく見極めるには、
実際の原料サンプルでの混合試験が最も確実です。
セイワ技研では、試験用混合機による混合テストを随時受け付けています。
混ざりにくい粉体や、比重差のある原料でお困りの際は、ぜひご相談ください。